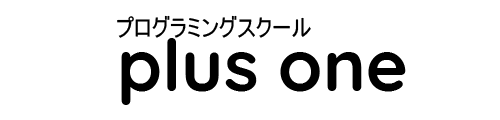お年玉から学ぶ、子どもの未来を育む『お金とプログラミング的思考』
明けましておめでとうございます。
お正月といえば、子どもたちが最も楽しみにしているのがお年玉ではないでしょうか。実は、このお年玉を通じて、私たちが大切にしている問題解決力と非認知能力を効果的に育むことができます。今日は、お年玉を活用した教育的アプローチについてお話しさせていただきます。
■ お年玉を通じた『論理的思考力』の育成
子どもたちは「限られたお金で何を買うか」という意思決定を通じて、自然と論理的思考を身につけていきます。例えば、「5,000円のゲームを買うと、3,000円の本が買えなくなる」という判断は、プログラミングにおける「if-then(もし~なら)」の考え方そのものです。
具体的なアプローチ例:
1.欲しいものリストの作成
- 優先順位をつける理由を考える
①必要度で考える:
「新学期に必要な文房具」→すぐに必要
「欲しいゲーム」→今はまだ遊んでいるゲームがある
「新しい習い事の道具」→来月から始まるので計画的に
②使用頻度で考える:
「毎日使う筆箱」→頻繁に使うので優先度高め
「たまにしか使わないおもちゃ」→優先度を下げても良い
「休日だけ使うスポーツ用品」→計画的に購入を検討
③時期による重要度:
「春の新学期用品」→今買うべきもの
「夏の水泳道具」→まだ先なので後回しにできる
「冬の防寒具」→セールで安くなる時期を待つ - 価格と価値の関係を話し合う
例:「3,000円のプログラミングの本は、新しい技術が学べて将来に役立つ」
例:「5,000円のゲームは、友達と遊べて楽しい時間が共有できる」
例:「2,000円の文具は、毎日の学習に使えて長く役立つ」
このように、モノの値段だけでなく、それを使って得られる経験や学びの価値を考える
2.予算内での最適な組み合わせ計算
- エクセルやメモを使って表にまとめる
- 複数のパターンを比較検討する
■ 『創造力』を刺激する使い方の提案
単なる「買い物」を超えた、創造的な使い道を子どもと一緒に考えてみましょう。
- 手作りお菓子の材料費として
- 家族へのプレゼント作りの資金に
- 募金や社会貢献への活用
これらの発想は、「お金の使い方」という枠を超えた創造的思考を育みます。
■ お年玉を通じた『社会性』の育成
お年玉の使い方を家族で話し合うことは、重要なコミュニケーション機会となります。
話し合いのポイント:
- なぜその使い方を選んだのか
- 家族や周りの人への影響は何か
- 長期的にどんな価値があるか
■ 保護者の皆様へのアドバイス
- 使い道の制限は最小限に
- 子どもの意思決定を尊重する
- 失敗も学びの機会として捉える
2.対話を大切に
- 「なぜそう考えたの?」と問いかける
- 決定プロセスを言語化させる
3.長期的な視点を育む
- 将来の夢と結びつけた使い方を考える
- 社会との関わりを意識させる
お年玉は、単なる「お小遣い」ではありません。子どもたちの論理的思考力、創造力、そして社会性を育む貴重な教育機会です。Plus oneでは、このような日常的な機会を通じて、お子様の総合的な問題解決能力を育んでまいります。
新年早々、まとまったお金を手にする機会だからこそ、ぜひ、お子様と一緒に「お金の価値」「計画性」「社会との関わり」について考えてみてください。